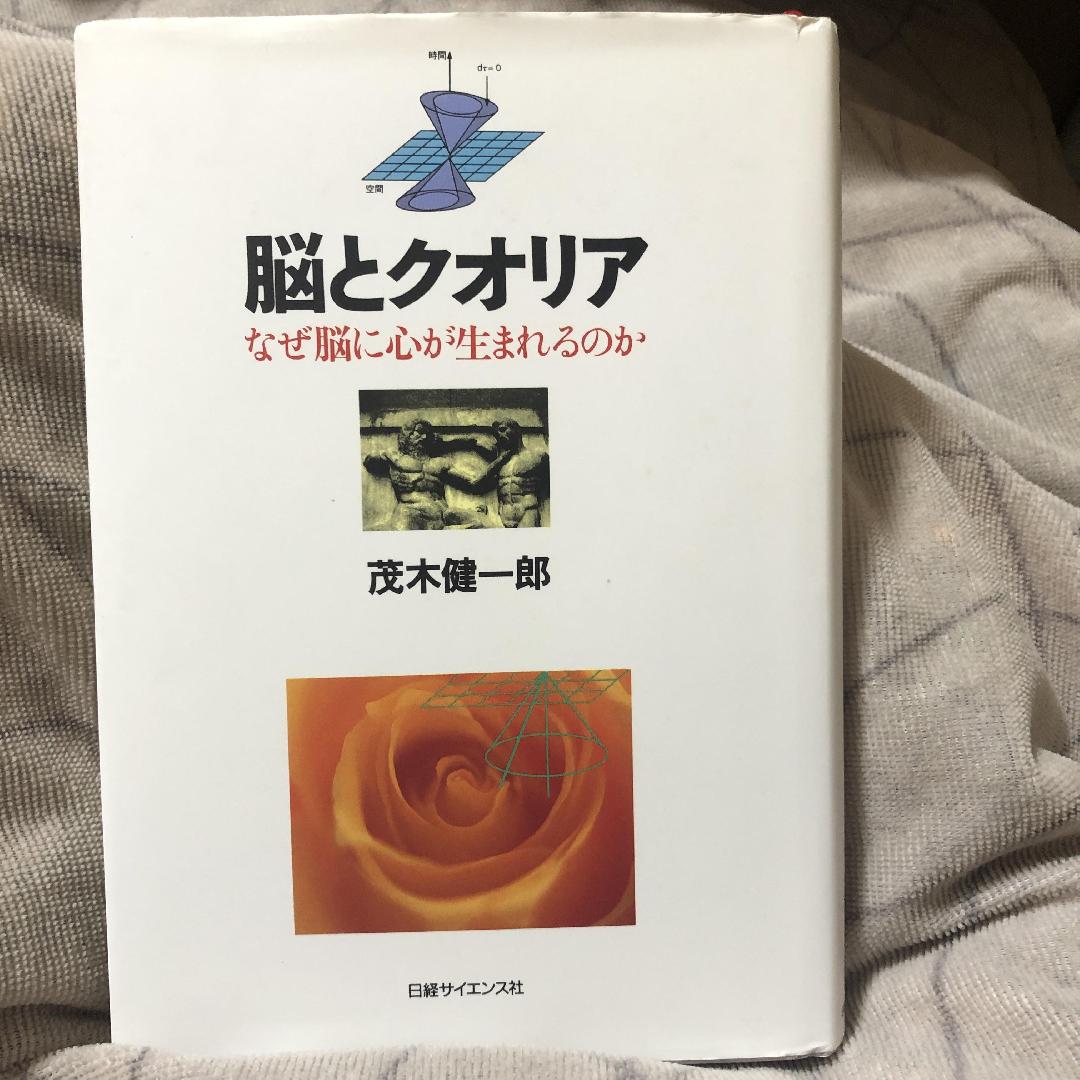『脳とクオリア』を途中まで読んで
〜なぜ脳に心が生まれるのか〜
(茂木健一郎氏。日経サイエンス社。1997)
1/5まで読み進めましたが、この一つ前に読んだ、『クオリアと人工意識』と合わせて、読んだ内容と自分の中の感想がグルグル混ざって一つのクオリアみたいになってしまっているので、今の状態をひとまずアウトプットします。
茂木先生の伝えたかった内容から離れていってるかもしれませんが、ない頭で必死についていこうとしての、今の私の精一杯です。
■人工意識の限界
意識や思考の完全再現や自分がどう思うかひらめきのタイミングを操ったり、人工意識でヒトの意識の完全コピーを作ることはやっぱり難しそうだ、、、
■思考、知識、経験、記憶
思考は、ことば、その文化の持つ概念や語彙の豊富さ、統語、文法、文脈に基づく。ことばには意味があり、使う内容には個人差があり、ことばの持つ意味や概念は、個人が過去に蓄積した経験、知識、そのとき感じた感情に影響される。そしてその知識もそれぞれ同様に過去に蓄積された語彙や文法、文脈により全体の意味が知覚される。
そのことばの積み重ねが思考となり、同じことばや概念を反復して再現すればその分、長期記憶となる。また、思い起こすためには、長期記憶となったときに、大脳皮質のパーツに分散されてかまとめてか分かりませんが、格納された時と同じ経路を辿ってニューロンの発火が再現することで、記憶から甦らすことが可能となるのではないかと。
記憶そのものは、かなり流動性があり、思い込み、勘違い、記憶違い、記憶の上書き、認知を変えるなど、再現時のこの神経のパターンは、意識的に又は、無意識に変動することもあるのではないかと。
夢や脳疾患、精神疾患などにより、幻視、幻覚、幻聴など、脳内でリアルに知覚する事象があるが、その人にはその瞬間それは真実として体験しており、今自分が感じている世界は脳が一旦受信したものを脳内で再現したイリュージョンであることは頷ける。
ビデオカメラが捕らえた映像なら、音も動画もそっくりそのまま記録できるところでしょうが、、、ヒトの脳はそうもいかない。著者が繰り返し命題として挙げている《認識とは私の一部である》の意味とは。
■脳の局在は外せない
また、脳には局在があることは既に知られているが、色を識別したり、形のエッジ部分を識別したり、音を周波数ごとに分析して音色や高さを感じたり、人の声と環境音を区別したり、人の顔を識別したり、身体の左右の感覚がわかり、手を伸ばせば目の前に存在する物体を掴むことができたり。
読み書きや計算、言葉を理解して、頭で考えた内容を言葉にして相手に返したりの一連の動作。方向や地理感覚、物体と自分との距離や離れたり近づいたりの速度を感じたり。どこかのルートに何らかの障害があると、経路を断たれるため様々な症状を呈する。
■思考、意識のまだまだ不思議
また、思考に関しては、積み上げられた体験に基づく記憶と記憶の連鎖であり、その時々の快・不快により、ことばの持つ意味、文法に適合するかフィードバックしながら紡がれるものではないか、と。以前関連つけて思い起こした内容は、似た体験が認知されると、紐づいて思い起こされ、その連鎖により近くの概念として格納されている記憶にも連鎖してニューロンの発火が起こるのではないか。
その起こり方に科学的な説明が可能なのか。確率や統計や数式で説明できる類のものなのか。筆者が繰り返し唱える《私たちの認識の特性は、脳の中のニューロンの発火の特性によって、そしてそれによってのみ説明されなければならない》というのは、とても深くて難題のように思われる。私たちが自分の思考だと思っているのは、脳が少し前に組み上げた体験を知覚しているだけなのか、、、それをヒトはあたかも自分が考えたもの、と捕らえているのか。
■経験ありきでは
赤の赤らしさ、薔薇の花のビロードのような質感、カエルを見たときの『気持ち悪い』感情は、体験として得たことや意味を理解した上での知識に照らして、かつてのニューロン発火パターンの再現や、例え見たことがない事象に対しても、経験則から類似したものと同様の反応が起こり、また、その発火パターンには過去になんらかの意味や感情が伴い、また、カテゴリーとして、ある概念とある概念が対比されたり、相関関係の中で評価されて初めてクオリアは生まれるのか。何か他のものとの違いがあって初めて、そのものが他でもないものといったイメージが生まれて、定着するのではないか。赤ちゃんサルが、針金でできた哺乳瓶付きの母親サル人形と、フワフワの温かな母親サル人形とでは、抱かれ心地よいフワフワを選ぶように、この話を例えにすることが適当かどうか分からないが、常に何かと何かを比べて選ぶを繰り返して脳は発達しているのではないか。しがみつく対象が例え人形でもそれを求めてしがみつくのは生物の本能として養育者を求める行動なんだろうとヒトも同じだと思うと感慨深い。
また、カエルの例が挙げられているが、見たことない動物を見ても、その動物にだけ反応する固有のニューロンなど恐らく1対1であらかじめ用意されている訳ではなく、過去に知覚した生物との類似点を抽出して危険な物と判断をくだせば、そのものに対する警告を旧脳が発して次の行動に反射的にうつる準備をしているのではないか。発火の連鎖の順番やパターンなど人により何をどう感じるか、次にどのような行動にでるかは変わってくる。その人個人の思考や行動を分析することで、過去データの全てがあれば、ある事象が起きたらどう感じ、どう行動するかの予測はつくかもしれないが、一個人に対してその分析を行う意味が見出せない。
■ノードとカテゴリー分け
赤の赤らしさ、『クオリア』に戻るが、例えばその質感に達するまでには、赤は、他の色と比較して、青でもなく黒でも白でもなく、と自動で識別したり、また、朱色や紫、茶色とは違うが、同色系で暖色系の色だと自動でカテゴライズしたり、また、知識としては、黄色の補色であるといった特徴や、赤と聞いて様々な思いが起こされる時、同時多発的にニューロンが発火することにより、それらのイメージが意識に上って来るのではないか。
赤と聞いて、そこには、視覚優位な人は赤いリンゴや赤い薔薇、赤い血の色を思い浮かべる人もいれば、派生して鼻血を思い浮かべたなら、血の混じる味を感じたり、視覚や聴覚が同時に働いた人は、パトカーのサイレンの音までがセットとなって知覚する人もいるかもしれない。青と聞けば、『珊瑚礁』と自然にイメージが上がってくるかもしれない。自動的に。一つのキーワードに沢山の意味を持つワードやそれに纏わるエピソードが紐づいてくる。マインドマップの枝や『記憶のノード』といったもののイメージを引用して。ここでも、視覚、聴覚、嗅覚などの五官(五感?)の役割は大きいし、第六感のいわゆる虫の知らせ的なものが、クオリアや下記のホムンクルスに当たるのかもしれないと漠然と感じる。
■ニューロン
ニューロンについて、例えば共感覚の持ち主の場合、隣接して並走する神経が、成長の過程でなんらかのねじれや配線の変異があったり(というような認識が私にはあるが)特定の一部のモダリティを介する場合のみ、知覚そのものがユニークな場合もある。特定の数字だけ色が着いて見えたり、ある音に色がついて見えたりその逆とか?詳しくないですが。これも10の11乗もの数の神経が胎内で細胞分裂を繰り返しながら伸びていき、脳の中では、DNAの地図に刻まれた通りのおそらく順番や道筋で神経細胞が発達し、落ち着き場所を探して伸びて収まるところまで伸びて、その際も常に周囲の細胞との距離感を保ち、シナプス間隙で神経伝達物質が受け渡しできるかできないかの絶妙な位置に収まる。まるで細胞それぞれが自分がどのように振る舞うべきかを知っているかのように感じる。
意識は、または、ホムンクルスのような小人が脳内の制御に携わっているとするなら、もしかして細胞一つ一つに実はその分身が備わっていて、発火するときには一つの集合体のように統合されて、一定の発火パターンをとるのではないか。著者がいうホムンクルス像からは離れてしまったかもしれないが。
■ひらめき
ニューロンの発火のパターンが思考と思考の合間や、朝目覚めたら、フラッシュのように発現してひらめきを覚えるときの現象は、普段から就寝時、夢を見ながら記憶を整理したり脳が活動を続けていて、思考はずっと無意識、水面下で続いていて、色んな神経の発火パターンは連続して起きている。知らないところで脳は考え続ける。それが無意識で行われているため、意識に上がるときには、ひらめきや、啓示のような第三者からのお告げのような神秘的な体験に繋がるのではないか。その発火と発火のパターンの間になんらかの次のパターンを誘発する物質があるのか、自動で偶発的に近くに位置する概念が、バリバリバリバリと連鎖して発火しているのか、そこは謎のままだ。
■直近の著書『クオリアと人工意識』からも
人工知能が文章を作るとき、初めの一文を与えてやると、過去のビッグデータから文法、語彙、文脈的に適した文章を作成するが、やはり、ヒトが物語のエンディングをあらかじめ定めてから試行錯誤しながら、話を展開させて全体的に方向性をコントロールするようにオチつかせることは困難があるようだ。やはり、ヒトの思考というか意識の変遷は、単なるニューロンが偶発的に発火パターンを連鎖しているだけには止まらず、そこになんらかの『1』『0』の配列以外にその場を支配する何か(何かという表現しか使えない時に、これもひっくるめて、クオリアという私にとってまだ掴みきれない表現を使いたくなる)の存在がちらつく。
■意識というクオリア?
意識や思考を考えると、ヒトと他の動物や昆虫とヒトを分けるその鍵はおそらくヒトだけが長い年月かけて進化させてきた大脳新皮質の前頭葉などの新しい部分にあるという説明が腑に落ちる。前頭葉が理性のコントロールセンターのように言われているが、他の脳の領域の発火パターンを予めプログラムして、発火の順番を決めると仮定して、そのヒトの意識を形作る。それも発火パターン同士それが持つ意味合いに、辻褄があうように、もし積み上げたストーリーが意味的に繋がっておらず、何らかの不快な情動が起これば、修正を繰り返しながら、、、前頭葉では、旧脳の情動の発火パターンも常にモニタリングしているといったマルチタスクをしているのではないか。まだ私には思考の元になる統合している存在、クオリアの正体が見えてこないが、人工知能が人工意識を持ち得ないのは、痛み刺激や冷感、嗅覚などが心に与える刺激のパターン、視覚、聴覚器官から脳内で再現されたときに感じる自律神経や快、不快、未来を期待する踊りたくなるような気持ちや過去の苦い経験に照らした抑うつ状態など情動の部分のクオリアをAIが感じることは難しいからではないか、と。『心の理論』と言われているような他者への共感性への問題をクリア出来た時、初めて、ヒトの心に近い人工意識に近付くのではないか。人工意識が、意識のメカニズムを完全に得ることができるなら、また、ヒトの思考パターンや感情を含めた神経の発火パターンを完全コピーできるなら、永遠の意識(命?)も可能かもしれない。脳の記憶容量ってほんとどうなってるんでしょう。
しがない通りすがりの一読者として、『クオリアと人工意識』に引き続き、『脳とクオリア』を読み始めましたが、1/5進まないうちに、なんだか、膨大に感じるところがあり、ストップしてしまい、なかなか残り4/5に進まないので、ここらで一旦今の作業を中断します。現実世界の自由時間が残り少ないので後は、一気に読みたいと思います。
今回の感想は、本からの引用部分の色分けを意識して行ってないので、そんなことは著者はゆってないぞ、な謎な部分がもはや入り混ざって、収集つかなくなってますが、本の影響を受けた後の今の私のクオリアがこれ、ってことで、一ブログ内での感想ですから、どうぞ許してください。文章も長過ぎて日本語もところどころ謎におかしいと思いますが。
専門用語が多数ですが、今ある自分の中の知識を総動員しながら、後半戦頑張って読みたいと思います。
まだまだクオリア、、、謎です。
→追記
読み進めるうちに、この受け止め方は明らかに著者の説明と異なる気になる部分を追記します。
①『赤の赤らしさ』というクオリアは、他の色とは関係なく、それに触れた時に単独で、感じる質感らしいです。
まあ、世の中に、赤しかなかったら、わざわざ赤を赤として識別する必要もないのかな、といった考えを私は持ちましたが、捉え方や表現としては、紛らわしい表現でした。
『青い珊瑚礁』ってのも、言葉の繋がりで『青』とくれば、補完的に慣用句として繋がるから、出てきやすい語として、挙げたものでクオリアとは関係ありません。ただ言ってみたかっただけです。『赤』とくれば、『スィートピー』みたいな。