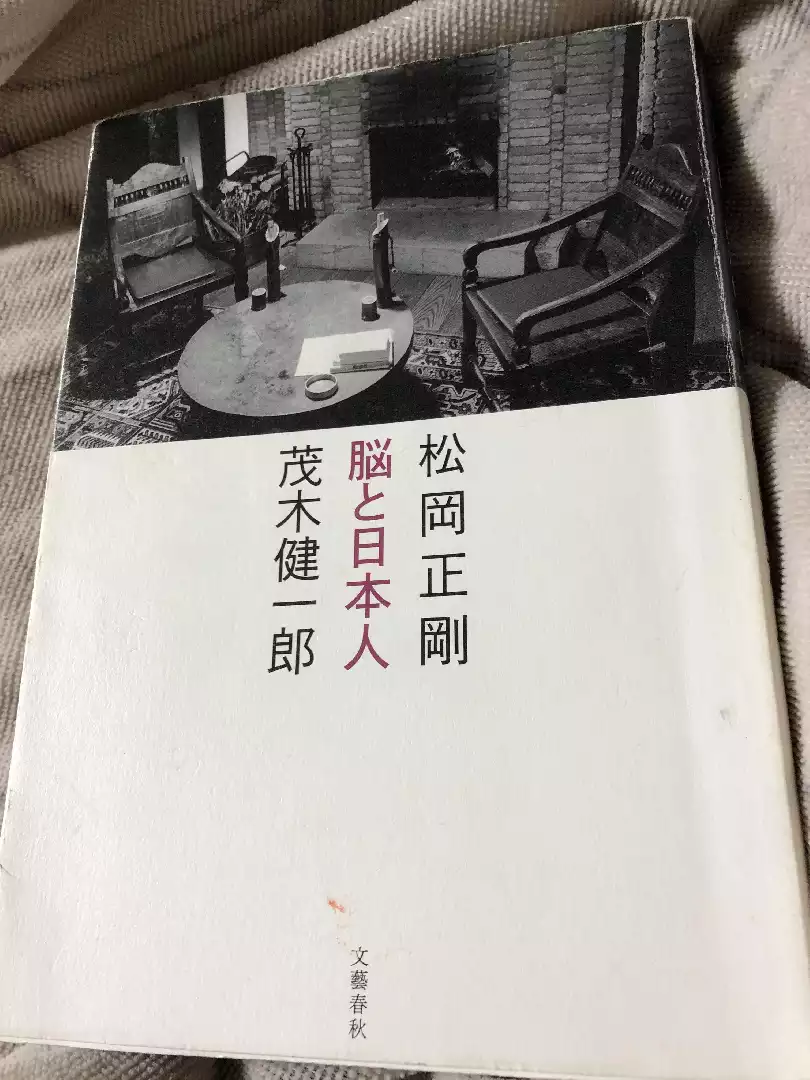『脳と日本人』
【松岡正剛、茂木健一郎著、文藝春秋、2007】
ちょっと何故この本をポチッて貰ったのかよく覚えてない。
多分、表装とタイトルと若かりし日々の茂木先生のトライアングルだったんだろうと思う。
これまで茂木先生の本は、手元に寄せたものは大体既に動画や音声ラジオを繰り返し聴いていたら、馴染みが深くツルツルっと読めていたのに、、、
これは、、、うぅぅぅむ、深い。
頭がついていかない。
お二人の深い会話を時空を超えて覗き込む感じ。私の方が歳上だ!茂木先生このアングル可愛い!などという楽しみ方や、別荘?や自然の写真が箸休めみたいに目の保養として、写真集としていけるんじゃない?ってくらいに、美しい。
しかし、内容が難しい!話題と展開が早くて、普通にしれっと共通言語のカタカナが、理解できない。何故横文字?と思いつつ、多分対訳がない概念なんだろう、私が知らないだけで、と自分を納得させる。
いやあ、知性のぶつかり合いってか、ビブリオバトル的な(よく知らないけど)。
とにかく世界史、日本史、言語学、宗教、科学、政治、経済幅広く論じておられるのですが、どれもこれも私は明るくないので、結局私も拾い読みみたいな感じになってしまいまして、、、
そして松岡先生の話がとにかく新鮮で、き、教授!って感じ。茂木先生じゃない方の松岡先生の話に度々引き込まれたのが、ちょっと予定外で。
そこ、ちょっと分からないよ、って気になるフレーズや響いたとこを、抜きます。
われわれは、ある種の時間の累々とした隔たりというものをバックに抱えている流れの中に存在しているわけです。時間はわれわれの中に潜んでいるともいえる。そういう意味では、時間の隔たりというのは、その大小、遠近を超えてわれわれの中にあるのではないかと思いますね。(松岡先生)
遠いということを、物理的な遠さに写像してもだめでしょうね。何かの記憶を呼びさますときには、今、この場所で呼びさましているわけですから。そこに、懐かしさとかが付け加わるのは、ものすごく不思議なことですね。(茂木先生)
→脳内で刻まれる時間の感覚について、また、記憶や感情との関係についてもっと知りたい。心をコントロールできたら、もっとずっと楽になるのに、、、
いまや日本は、とんでもないものになりましたね。たとえば、いじめの問題や社会的逸脱者にしても、アノマリーなものを絶対に許せない。(松岡先生)
→いじめられた側は、まさか自分がと思うからなかなか声をあげられない。いじめた側はこれがそうだという自覚がないから、なかなか自ら気付かない。目に見えない現象で鍋の灰汁のようなものだと私は考えてます。
いじめについて、見聞きしたり原体験として語れない人で、自分には関係ない他人事、理解できない世界の話と考える人は、まさに、無意識でやってる側の可能性が高い。ハラスメント全てに共通する。やる側、やられる側、傍観者の自分の立ち位置はどれか。それを受けての行動は人それぞれ。感じ方も人それぞれ。
筆は中国で育ちましたから、太極拳とか、いろんなものとワープしあっているのですね。筆の軸の長さ、それに筆を持っている形というのは、身体の根本的なストロークを反映した所作になっているために、道具的に筆から別のものに移れるのね。(松岡先生)
→その他にもハンドル操作の上達に箸を使う話や身体性の話も興味深い。使える感覚を研ぎ澄ませて、他の機能に作用するという感じかな。昔習字を長くやってきて、大筆なら綺麗に書けるのに、あとの所作が何もかも雑破な私の強い癖は、もしかして、また、筆を突き詰めたら何か分かることがあるのかもしれない、、、
また、松岡先生は、元F1レーサーの鈴木亜久里さんからの話で、身体の身動きがとれないため、車の動きを制御するために、センサーとして鍛えるのは、お尻の穴だ、という話もされていて、使える感覚は不自由さがあればその分、通常の状態を超越する能力を発揮するのかな、、、と。
身体に障害がある方で口や足で筆を使われて絵を描かれる画家さんの作品を拝見しましたが、とても素晴らしかったです。
脳の仕組みからいうと、身体イメージはほんとうに複雑なんです。身体性をフィジカルな形態とか構造としてとらえようとするととらえ損なってしまいます。数式のような抽象的な思考が、いかにわれわれの上-下、中-外、表-裏とかという身体的なメタファーによって支えられているかという議論を(略)、われわれは、自分の身体をこれまでの幾何学ではとても扱えない、複雑な概念の集合体として把握しているのです。(茂木先生)
→茂木先生は、よく身体性という語を使われます。脳内で、知覚や記憶が統合されて、思考や次の行動へのプログラムが実行される。どれか一つ障害されるとこれまで通常運転してきたはずの振る舞いから外れてしまう。病気や怪我や老化や薬の副作用や、或いは生まれつき脳の個性として、、、どう折り合いをつけたり、別のルートを使って補うかってことが、大切なのかなあと思います。
ミラー・ニューロンの反応特性は、相手の行為を見た際に、それをあたかも自分がしているかのようなシミュレーションを実行することを可能にします。つまり、「相手が今、こういう行動をとっているということは、私がこういう行動をとるということに相当する。ということは、その背後にある心的状態は...」という推定ができるわけですね。(茂木先生)
→茂木先生のこういうところが、私が痛く共感する所以なんだろうな、と思う。
そのうちに、いつしか克服して(吃音症状を)、言いたかったことが言えるようになった。ところが、喋ってみると、なにかアタマの中にあったものと違う感じなんですね。で、「あれが言いたかった」「これが言いたかった」と思う訳ですね。じゃあ、アタマの中の吹き出しの中のものは、言葉じゃないのだろうか。そういうことが疑問になった。言語学ふうに言えば、内語と外語は違うのか、内語以前というのはあるのだろうか。(松岡先生)
→松岡先生の過去の吃音症状や目の不自由な親戚の方の物凄い聴力の話は、実体験としてとても印象的ですし、私は言葉全般に興味があるので、頭の中でどういった仕組みで言葉が紡がれるのか、どのようにして形に現れるのか、まだまだ知らないことばかりでよい刺激を受けました。
また、松岡先生の幼なじみの女性が、ある時ガス自殺を図り記憶喪失となったけれど、ある日銀杏の木の下で、過去の記憶が蘇った瞬間があった、と。場所とトポグラフィック・メモリーか、コンテクスチュアル・メモリーかが、何かでつながっているのではないか、と感じられた、と。
失われた記憶を一部でも呼び起こすのに、当時発火した神経パターンが、その場面とともに紐付けられたであろう、木漏れ日の眩さや、銀杏の香り、実を踏んでしまったときの足裏の感触や、遠くで聞こえた音や声が引き金となり、再現される。茂木先生が言われるクオリアってこういうことですかね、、、
また、一緒に隣を歩いていた人に対する秘めた思いなどのエピソードが相互に補完しあって記憶の想起に繋がったのかな、、、と思います。記憶は失われたのではなく、奥底に眠っている。その回路を活性化させるか、他の迂回路が繋がれば、のぞみはあるのか、、、
私は可能性として、音のバイブレーションというか倍音が脳の活性化にいいんじゃないか、という仮説を密かに抱いています。学生時代、合気道の合宿で、一度だけバイオンを経験しました。「おー」とか「うー」とかを息の続く限り、ひたすら発声するのですが、自分が音階を微妙に上げ下げしてるうちに、頭の中で音が響いた感覚が忘れられないんですね。耳鳴りみたいな嫌な感じとかでは、全くなくて、、、ちょっと未知の世界に持っていかれそうな神秘性は感じましたが。
誰か代わりに証明してくださったら、、、侵襲性も中毒性もないと思うし、声出すだけだからエコだと思うのですが、、、人数がいりますけど。やり過ぎなきゃ身体にも心にもよいと思うのですが、、、
近いもので、お寺さんの御詠歌とかもそんな感じですかね、、、分かりませんけど。
たとえば、注意をシフトするにはおよそ1秒かかります。自分が何かをやって音が生じるときに、行為と音の間隔をずらしてやると、脳が自分の行為と結果として出る感覚のフィードバックを関連付けて解釈しようとして、実際の物理的感覚よりも短く知覚するとか、最近そういう研究が出てきています。(茂木先生)
→視知覚の心理学の分野ですかね。錯覚、錯視、視覚と聴覚の優位性や色や動き、距離、大きさ、形の輪郭など脳は、こうあるべき、って風に知覚するように微調整してるんですよね。私はどうも鈍感なようで、授業で一人置いてけぼりをくったのですが、ちょっと恥ずかしくて、もう一回お願いします、って言えなかった。若かったなあ、、、
象とネズミの寿命が違うように、私は同じ人間でも、心拍数の関係もあるだろうし、性格的にのんびりさんと、セッカチさんの間では、体感の時間の速さも違えば、なんなら、寿命にも影響するんじゃないか、と個人的に昔から思っています。
もっと、外国や日本の神話や国学、言語学、民俗学、宗教、歴史、国民性など対話は多岐に亘るのですが、私には高度過ぎて読書ペースもなかなか進まなかったのですが、自分が、気になる部分だけでも、アウトプットしてみると、相当中身の濃い本でした。
また、ご興味ある方は、買うなり借りるなりしてお確かめください。
スマホでポチポチ打つ量を超えてました。
おやすみなさいませ。
最後まで、読んでいただいた方、ありがとうございました。